
公開日: 2016/06/16
嬉しい時もつらい時も
なぜかパチンコ やっぱりパチンコ
暑いといえばパチンコ
寒いといえばパチンコ
時間があってもなくてもパチンコ
ついついパチンコ
姿カタチは変わってもパチンコの想いはひとつ
もっと楽しく もっと愉快に
もっとわくわく面白く…
これは、図書館で発見した「パチンコミュージアムの図録」の冒頭付近に書かれている一文です。引用させていただきました。
正村商会本社ビルの3階にあったパチンコミュージアムの入口付近にも、おそらく同じ文言が書いてあったのでしょう。
このパチンコミュージアムは、ただ単に古いパチンコ台のコレクションを並べて展示していただけではありません。パチンコ黎明期の歴史を深く掘り下げ、そもそも、いつどのタイミングでパチンコはパチンコたりえる存在となったのかを様々な角度から考察しています。
そして、「パチンコのルーツは大正末期にアメリカから輸入されたコリントゲーム(=スマートボールのような横置きの遊戯機)である」という当時の定説に疑問を抱き、時間をかけて真相を究明していった、その過程も展示していたようです。
これが、じつに興味深い。
日工組のエラい人ですら、その定説を信じていたらしいんですよ。しかし平成7年頃、このパチンコミュージアムの展示内容をリニューアルする際に調査や取材を積み重ねていったら、違う結論に至ったと。
※正確に言うと『パチンコミュージアム』ではなく、『パチンコミュージアム第2章』です。
正村ビルが完成した平成3年から5年間ほど「正村竹一資料室」として一般公開されていた場所を、平成7年頃に展示内容をリニューアルし、新たに『パチンコミュージアム第2章』という名前にしたという経緯があったからです。
この、リニューアルされた後の『パチンコミュージアム第2章』に、パチンコ黎明期の興味深いあれこれが展示されていたというわけなんですね。
今回、図書館から本を借りてくることはできませんでしたが、内容の一部をコピーして持って帰ってきました。
『調査研究を目的とした場合に限り、著作権法の範囲内でコピーすることができる』――名古屋市立図書館の利用ルールより
白黒だけじゃなくカラーコピーもOKとのこと。
「パチンコ発祥の地はドコなのか?」という疑問を解決するための調査研究ですからね、これは。
(´・ω・`)キリッ
【おまけ】
発祥の地に迫っていく前に、小ネタを少々。

伝統の正村マーク。
『正村』の文字の周囲に玉が10コ。これは昭和25年頃、正村ゲージの開発とともにヒットしたパチンコ機「オール10」にちなんでいるんだとか。
なるほど~~~~。
その正村ゲージを開発する際、もっとも肝になった部分は「風車」なんだそうです。
風車を取り付けたことにより玉の動くスピードが増し、思いもよらぬ方向に飛んでいく面白さがあるわけです。
で、その風車を思いついたキッカケが、その昔、岐阜市茜部にあった水車らしいんですよ。のどかな農村だった当時の、田んぼと水路が広がっていたであろう風景が発想の根幹にあったのだと。
まずは風車を据え、そのあとで周辺のクギの配列を工夫していった結果として「正村ゲージ」が完成したという考え方もできるんだそうです。
ちょっと大げさですが、今日(こんにち)のパチンコ業界があるのは岐阜市茜部にあった水車のおかげなのかもしれません。
ライター・タレントランキング
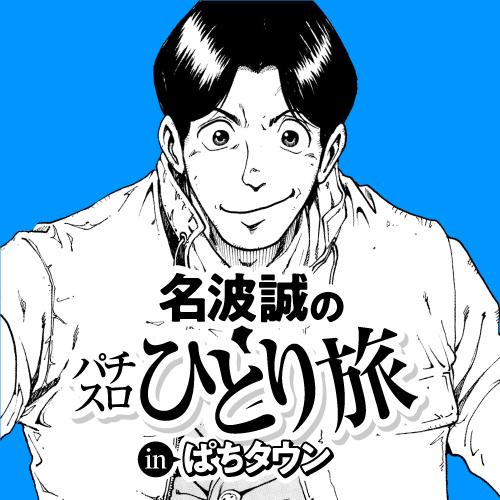



/208424.jpg?t=1769998375)
/192410.jpg?t=1752060021)

